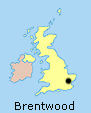| はじめに | |
| 1 | 父方の家系 |
| 2 | 母方の家系 |
| 3 | 両親 |
| 4 | 幼年期 |
| 5 | 義母の家系(父の再婚相手) |
| 6 | 義父の家系(母の再婚相手) |
| 7 | ブレントウッド・スクール |
| 8 | ギャップ・イヤー |
はじめにダグラス・アダムスが有名作家になるまでの経歴を紹介するなら、ざっとこんなところだろうか。
1952年3月11日、ケンブリッジ生まれ。父親のクリストファー・アダムスはケンブリッジ大学で神学を専攻する大学院生、母親のジャネットは看護師だった。アダムスが5歳の時に両親は離婚、アダムスは3歳年下の妹スーザンと共に母親に引き取られ、母親の実家があるブレントウッドに移る。1959年、ブレントウッド・スクールに入学。1971年、ケンブリッジ大学に進学、英文学を専攻した。卒業後、グレアム・チャップマンと組んでラジオやテレビのコメディ番組の製作に乗り出すも、何も実現しないまま二人の関係は半年ほどで終了する。1978年、ラジオ・ドラマ『銀河ヒッチハイク・ガイド』が大ヒット、翌年出版した小説『銀河ヒッチハイク・ガイド』もベストセラーとなった。
一作家の生い立ちについて、これ以上の情報は無用の詮索かもしれない。と思いつつ、これから私がアダムスの生い立ちについて微に入り細に亘って記述しようとするのには、二つの理由がある。
一つは、日本と異なる文化的背景や学校制度が単純に興味深かったからだ。そしてまた、日本とはいろいろな面で異なる環境にありながら、それでも詳細に目を凝らせば、家族の問題やその関係性は決して似て非なるものではないとわかったからでもある。
もう一つの理由は、これから紹介する内容はアダムスの公式伝記 Wish you were here: the Official Biography of Douglas Adams と、非公式伝記 Hitchhiker: A Biography of Douglas Adams、それから Don't Panic: Douglas Adams & The Hitchhiker's Guide to the Galaxy の3冊で既に公表済みことだから。とりわけ、アダムスの親族に関する情報は公式伝記に依るものであり、ということは私がことさらにアダムス本人ならびにご遺族の方々のプライバシーを暴き立てたと非難される恐れはない。その分、独自調査も何もあったものではないと言われてしまえばそれまでだが。言い訳はこのくらいにして、まずはアダムスの父方の祖先から紹介しよう。
1 父方の家系アダムスの父方の先祖は、スコットランドで代々医業に従事していた。過去4世代に遡ると、11人の男性医師と女性外科医を輩出したという。
その4世代前、アダムスの祖父の祖父にあたるアレクサンダー・マックスウェル・アダムス(1792-1860)は、エディンバラ大学を卒業し、エディンバラで医師として働いていた。
公式伝記でによると、彼が勤務していた病院はアーガイル・スクエアという場所にあったとのことだが、ということは1704年に設立された Trades Maiden Hospital のことだろうか。だとすれば、この病院はその後 Melville Street に移転し、19世紀半ばにはアーガイル・スクエアの跡地に博物館(the Museum of Science and Art)が建てられている。この博物館も、後に組織の統廃合に伴って名称が何度か変更され、現在は国立スコットランド博物館(National Museum of Scotland)と呼ばれている。エディンバラ大学のすぐそばに位置し、実際、博物館が所有しているコレクションはエディンバラ大学と関わりがあるらしい。話をアレクサンダーの時代に戻すと、19世紀初頭当時、エディンバラ大学では医学に関しては世界でも最先端レベルの研究が行われていた。18世紀の、いわゆる「スコットランド啓蒙」と呼ばれる世相を背景に、大学のカリキュラム改革などが積極的に行われた結果、「十八世紀末のエディンバラ大学では神学教授のポストより医学教授のそれのほうが多くなっていた。ポストの数だけではなく、エディンバラは同じ頃すでにヨーロッパで並ぶもののない医学教育センターとなっていた」(高橋哲雄、p. 173)という。チャールズ・ダーウィンは、ちょうどこの時期にエディンバラ大学で医学を学んでいるし、それから約50年後にはアーサー・コナン・ドイルが学んでいたことでもよく知られている。アレクサンダー・マックスウェル・アダムスが医学生として学び、医者として働いたエディンバラは、医学に関しては決して単なる一地方都市ではなかったのだ。
アレクサンダー・マックスウェル・アダムスは、治療費を払えない貧しい人々の治療も積極的に行うタイプの医者だった。その一方、医学の教科書や、医師としての実体験をまとめた Sketches from the Life of a Physician という本を執筆し、さらには詩集や小説を手がけたこともあったとか。概して人望が厚く、評判も良かったらしい。このことが、1828年、エディンバラのみならずイギリス全土を震撼させたバークとヘアの連続殺人が発覚した時に、アレクサンダーの窮地を救うことになる。
この時代、医学の発達に伴って解剖用の死体の需要が増え、死刑囚の遺体だけでは足りなくなっていた。そのため、ホームレスの死体を見つけて売るだけでなく、遺体を墓から掘り出す、いわゆる死体泥棒が横行したが、バークとヘアの二人は、遺体の不法入手にとどまらず、生きている人間を16人も殺害し、その遺体を解剖学教師ロバート・ノックスに売って金儲けをしたのである。R・D・オールティック著『ヴィクトリア朝の緋色の研究』によると、バークとヘアは、病気、アルコール中毒、祖末な食事、老いによる衰弱に拍車をかけることによって、自分たちの商品を生産するうまい方法を思いついた。衰弱状態の原材料に出くわすとーースコットランドにはこの手の者はうじゃうじゃいたーー、ふたりは次のような立証済みのやり方でそれを料理した。まず安酒を気前よく奢って、ゆくゆくは死体となる人間をこちらの言いなりの状態にする。それから手と膝を喉元にあてて強くおさえる。いまやこのやり口は、burke(=扼殺する)という動詞になって、正式に英語の語彙のひとつとなっている。ここまでくれば、あとは商品の新鮮さを誇るバーク・アンド・ヘア迅速配達会社が、品物をノックス博士の「博物館」へ送り届けるだけ。(略)取引きは双方が望むとおり、なるべくビジネスライクにおこなわれた(p. 44)。
これが、アレクサンダー・マックスウェル・アダムスが生きていた19世紀初頭の、世界最先端を誇るエディンバラ医学界のもう一つの顔だった。公衆衛生や麻酔学など、近代医学の基礎が築かれつつある一方で、優秀な解剖博士だったはずのロバード・ノックスは、「バークとヘアが彼に売ったなま新しい死体がどこから来るのか、信じがたいほど無関心でいられた」(同、p. 211)。
とは言え、エディンバラの市民がそれで納得したはずもなく、この事件が明るみになると、アレクサンダー・マックスウェル・アダムスはこのノックス博士と間違われて群衆にリンチにかけられそうになったという。彼が危うく難を逃れることができたのは、怒れる群衆の中の一人が、日頃病院で勤務している彼の顔を覚えていてくれたおかげだった。ロバート・ノックス本人は、結局、死体の出自について知らなかったという理由で罪に問われることはなく、集団リンチに遭うこともなかった。************
アレクサンダー・マックスウェル・アダムスは、三人の息子に恵まれた。ウィリアム・デイヴィッド、ジェイムズ・マックスウェル、そしてアレクサンダー・マックスウェル。三人とも医者となり、ウィリアムはエディンバラ、ジェイムズとアレクサンダーはグラスゴーで、それぞれ立派なキャリアを築いた。
この三人のうち、アダムスの曾祖父にあたるのは、次男のジェイムズ・マックスウェル(1817-1899)である。彼はグラスゴーに出て医学の技術を磨くかたわら、毒物学や工学にも関心を寄せ、呼吸器系の病気の患者が使用する、安価で扱いやすい吸入器を開発したりもした。
父のアレクサンダー・マックスウェル同様、ジェイムズも意外な形で当時グラスゴーを震撼させた有名な殺人事件と関わりを持つこととなる。その事件とは、1865年、医師のエドワード・プリチャードによる妻と義母の毒殺。プリチャードは、食物の中にアンチモンを混ぜ、まず義母、それから妻の順に、ゆっくり残忍に殺していったのだ。アコニチンやアヘンにも手を出したが、おそらくアンチモンほどふんだんには使わなかった。何種類かの毒物を異常なほど多量に買い込んだことが証明されている。グラスゴーでもいちばん大きな薬局のひとつは、ある年、その町の他の医者に売ったのと同じ量のアンチモンをプリチャードひとりに売った。「今までに、これほど大量の毒物をひとりの医者に売ったことは一度もない」と、店主は語った。だから、この不運なふたりの女性の死体を解剖してみると、命取りとなった毒薬が身体中にしみわたっていたが、それもそのはずだ(オールティック、p. 240)。
ジェイムズは、この犯罪を立証するための法医学的検証を行ったらしい。そんなにも大量のアンチモンが使用されたのなら検証するのはそう難しいことではなかったのではないかとも思うが、プリチャードの事件のわずか6年前、やはり医師のスメサーストが女性毒殺の嫌疑をかけられた際には、「著名な専門家テイラー博士」(同、p. 230)による検屍処理の不手際により、(有罪判決は出たものの)特赦になっている。宣誓証言の場で自らの過ちを率直に認めたテイラー博士の態度は立派だが、ロンドンの法医学の権威が手がけていてさえこの有様なのだ。ジェイムズにとって、グラスゴー中の注目が集まるスキャンダラスな殺人事件で検屍にミスがあってはならないというプレッシャーは強かったのではないか。
果たして、エドワード・プリチャードは絞首刑となった。ちなみに、この絞首刑はグラスゴーで最後に行われた公開処刑であり、一説によると10万人もの見物人が押し寄せたと言われている。スコットランドの首都エディンバラに対し、グラスゴーは18世紀後半以降の産業革命で経済的に大きく発展した街である。この時期、商業活動の活発化に伴い、グラスゴーには次々と新しい銀行が誕生した。そして、グラスゴー在住の多くの中流市民たちはこれらの銀行の株式を保有するようになる。ジェイムズもまたそうした中産階級の一人だったが、1878年10月、彼が株を所有していたグラスゴーの銀行が倒産し、自宅を売却する必要に迫られることになる。
ジェイムズが株を保有していたとされる銀行は、公式伝記には "the Bank of Glasgow" と書かれているが、倒産時期から考えてこれはシティ・オブ・グラスゴー銀行(City of Glasgow Bank)のことだろう。この銀行が設立されたのは1839年、当時のジェイズムは20代前半だった。ということは、シティ・オブ・グラスゴー銀行は設立から40年とたたないうちに倒産したことになる。
シティ・オブ・グラスゴー銀行の倒産は、グラスゴーを揺るがす大事件だった。この事件については、1997年に出版されたスコットランド系イギリス人作家ジェイムズ・バカンの著書『マネーの意味論』に詳しい。というのも、ダグラス・アダムスとは同世代にあたる1954年生まれのジェイムズ・バカンの大曾祖父ジョン・バカンもまた、この銀行の倒産によって負債を背負わされた一人だったからである。一八七八年十月二日、グラスゴー・シティバンク(註・この本では、"City of Glasgow Bank" は「グラスゴー・シティバンク」と訳されている)は破綻した。この日、銀行業務を停止して店じまいしたこの破綻は、連合王国(The United Kindom:日本で俗にいう英国)史上、最悪の銀行破産であり、これでスコットランドの銀行資本は一〇分の一以上を失ったのである。(略)
当時、英国(大英帝国)の共同資本銀行(現在の商法では「合資会社」。無限責任社員と有限責任社員が共同して作る会社)の株主は、ただの株式受託人にすぎなくても、(無制限の債務を負う)無限責任を引受けさせられるリスクにさらされていた。つまり、株主は、株式の額面価値のみならず、自己の保有する全財産をなげうって応分の負債を弁済するリスクを背負っていたのだ。(略)清算管財人たちは、グラスゴー・シティバンク預金者や同銀行券(banknotes いわゆる紙幣)保有者に弁済するために、六○○万ポンドの資金を必要としていた。取り立ての唯一の相手は、一二四九人の株主とパートナー(共同出資者)であり、その多くはグラスゴー、エジンバラ、アバディーン、それにイングランドとスコットランドの境界地方の小市民か中流程度の暮らし向きの人びとだった。十月二十五日、清算管財人たちは、全ての株主に対して、株式額面一○○ポンド(の一株)につき五○○ポンドを拠出するよう第一回目の払い込みを請求してまわった(pp. 268-269)。弁護士だったジョン・バカンは、支払いを免れようと訴訟を起こしたが認められず、棄却された。そして、「バカン氏は、課せられた分担金を弁済した。しかしこれで彼は、財力精魂ともに尽きてしまった。あらゆる証拠からみて、死んだときは一文なしの身空であった」(同、p. 270)。
バカン氏と比べれば、ジェイムズはまだしも幸運だったと言える。父親のアレクサンダー・マックスウェル・アダムス同様、ジェイムズもまた患者たちから慕われる医者だった。ジェイムズが自宅を売らなければならないと知った彼の友人や元患者たちは、彼のために家を買い戻してくれたのだ。そして、家の権利証書を入れた銀の小箱を彼にプレゼントしてくれたのだという。
グラスゴーの急激な経済発展は街に繁栄をもたらす一方、労働者の流入による人口増加でスラム街を形成することにも繋がった。『図説スコットランドの歴史』の著者リチャード・キレーンに言わせれば「それはまた、グラスゴーでもっとも悪名高いスラム地区ゴーバルズに象徴される、極貧の恐るべき生活水準をもたらした。ゴーバルズのスラムといったら、先進世界で並ぶものが他にないほどの、人間らしさが失われる困窮の巣窟となった」(pp.178-179)らしい。
無論、ジェイムズ・マックスウェル・アダムスとその家族は、シティ・オブ・グラスゴー銀行の倒産に際してたとえ本当に自宅を処分することになったとしても、さすがにゴーバルズへの引っ越しを余儀なくされることにはならなかっただろう。が、当時12歳だったジェイムズの息子、ダグラス・キンチン・アダムスに何らかの暗い影を落としたかもしれないーージョン・バカン氏の孫で、後にイギリスのスパイ小説の元祖の一人となるジョン・バカンが、「貧困はわが歴史における最初にして最大の事実で、わが民族はきびしい学校でなければ身につけてくれぬいくつかの性質を貧困から学びとった。努力しなければ何も得られないこと、いちばん大切なものはいちばん費用がかかるものだ、ということだ」(高橋哲雄、p. 199)と語るとき、そこには「それとはなしにグラスゴー・シティバンク破綻の余波が感じられる」(バカン、p. 281)ように。
アダムス家が家族の深刻な財政危機を美しい銀の小箱のエピソードに収斂することができたのは、とびきりの僥倖だったと言うべきか。
************
アダムスの祖父ダグラス・キンチン・アダムス(1891-1967)の「キンチン(Kinchin)」というちょっと変わった名前は、彼の母親の旧姓による。ダグラス・K・アダムスは、優秀な医者揃いの一族の中でも飛び抜けて優秀だったらしい。グラスゴー大学で学び、内科と外科の学位を取った上、産科学、外科学、病理学、法医学の分野で一位になった。おまけに、理学士と文学修士まで優秀な成績で取得したという。医療の実践と研究の上でもすぐれた業績を残し、中でも20世紀初頭の当時は治療不可能と考えられていた神経系の病気の分野に挑んで、多発性硬化症の治療に光を与えた。この治療をテーマに書かれた彼の博士論文は、グラスゴー大学からベラハウストン・ゴールデン・メダルを授与されている(ただし、M・J・シンプソンによるアダムスの非公式伝記には、父方の祖父は耳鼻咽喉科の専門医だったと書かれている(p. 7)。公式伝記の記述と矛盾するようだが、神経内科のような医学領域から耳鼻咽喉科に移ったのだろうか?)。
1914年に第一次世界大戦が始まると、戦争に行かなくていい理由も資格も十分にあったにもかかわらず、ダグラス・K・アダムスは周囲の反対を振り切って海軍に自ら志願した。そして、軍医として巡洋戦艦に乗ることになる。二度ばかり魚雷の攻撃を受けたこともあったらしいが、幸い大きな怪我をすることもなく、28歳でグラスゴーに戻った。
終戦後、グラスゴー大学でダグラス・K・アダムスが行った医学の講義は、従来の医学の講義とは似ても似つかないとびきりのおもしろさで学生たちを引き付けた。孫にあたるダグラス・N・アダムスの聴衆を魅了するスピーチの巧さは、父方の祖父譲りと考えて間違いないだろう。
ダグラス・K・アダムスは、長年に亘ってグラスゴーの西部病院(Western Infirmary)で顧問医師を務めた。この病院はグラスゴー大学の付属医療機関で、グラスゴー大学が街の中心から西部地区に移転するのに伴い、1874年に建てられている。設立当初はベッド数150程度だったが、1911年までには600を越えていたというから、ダグラス・K・アダムスが勤務していた時代ならかなり規模の大きい病院だったのではないだろうか(現在のベッド数は約500。2013年には、やはりグラスゴー大学の付属医療機関である別の総合病院に合併という形で閉鎖される予定)。かくして医師としての彼の名声は、グラスゴーでは確たるものとなっていった。
1929年の大恐慌の際には個人資産を失ったりもしたが、本人はあまり気にしていなかったようだ。彼の父親であるジェイムズ・マックスウェル・アダムスがシティ・オブ・グラスゴー銀行の倒産で被った損害と比較してどちらがより深刻だったのかは知る由もないけれど、ともあれ二人とも生活が成り立たなくなるほどのことではなかったのだろう。
************
大恐慌と前後するこの時期、ダグラス・K・アダムスに息子が誕生した。クリストファー・アダムス、すなわちダグラス・アダムスの父親である。クリストファーの生年月日は、公式伝記等には明記されていない。ただ、亡くなった年とその年齢から推測して1928年か1929年の生まれではなかったかと思われる。ダグラス・キンチン・アダムスの息子クリストファーは、医師にならなかった。
2 母方の家系アダムスの母方の家系に関しては、父方ほど詳しいことは公表されていない。ただ、曾祖父(great-grandfather)がドイツの有名な劇作家兼俳優のフランク・ヴェデキント(1864.7.24-1918.3.9)であることは知られている。
ベンジャミン・フランク・ヴェデキントは、19世紀末から20世紀初頭にかけてミュンヘンを中心に活躍し、若き日のブレヒトにも影響を与えた。代表作には、ルル二部作の『地霊』『パンドラの箱』や、2006年にブロードウェイでミュージカルとして上演された『春のめざめ』等がある。既成の社会概念に揺さぶりをかけるような作風で知られ、ドイツ表現主義や不条理演劇の先駆ともみなされる。Marilette Van der Colff は研究論文 "Douglas Adams: Analysing the Absurd" の中で、ヴェデキントの不条理のテイストは『銀河ヒッチハイク・ガイド』に相通じるものがあると指摘しているが(p. 5)、アダムス自身がどの程度この高名な先祖のことを意識していたのかは不明だ。
ちなみに、フランク・ヴェデキントの父、フリードリヒ・ウィルヘルムは医師だった。つまり、ダグラス・アダムスの先祖には、父方にも母方にも医師がいたということになる。
そのフリードリヒ・ウィルヘルムは、医師としてトルコのスルタンに仕え、1948年のトルコ革命の翌年、アメリカに渡った。そしてサンフランシスコで出会ったドイツ系スイス人の歌手エミーリエ・カメラーと出会い、結婚する。岩波文庫『地霊・パンドラの箱』の解説によると、フランク・ヴェデキントの「音楽的才能はこの母の家系によっている」(p. 291)とのことだが、ということはつまり、ダグラス・アダムスの音楽的才能もささやかにその恩恵を被っているのだろうか?
ベンジャミン・フランク・ヴェデキントは、パメラ、カディージャという二人の娘に恵まれた。この二人の娘のうちのどちらかがイギリスに嫁いだのか、あるいはフランク・ヴェデキントの兄弟(彼は6人兄弟だった)のうちの誰かがイギリスに渡ったのか、そこのところはよくわからない。が、詳細はどうあれ、彼らの子孫にあたるアダムスの祖父母のドノヴァン夫妻は、遅くとも20世紀半ばにはエセックス州ブレントウッドに居を構えることになる。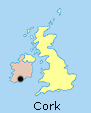
アダムスの祖父のミスター・ドノヴァンは、元々はコーク出身のアイルランド人だった。アダムスいわく、イングランド在住のアイルランド人にありがちな、アイルランド在住のアイルランド人よりもずっと典型的なアイルランド人で、「65歳の誕生日に仕事を退職して帰宅すると、『やるだけのことはやった、今から寝る』と行って床につき、そのまま7年間、死ぬまで横になっていた」(Hitchhiker, p. 7)という。かくして、アダムスが物心ついた時には、祖父は病気で寝たきりだった。
祖母のミセス・ドノヴァンは、善良な女性ではあったが子供や孫を猫かわいがりするタイプではなかったらしい。どちらかと言えば人間よりも動物が好きで、動物愛護団体 RSPCAの熱心な活動家として地元ブレントウッドでは特に知られていた。時折、ブレントウッドのメイン通りを、小脇に怪我をした白鳥を抱え、片手で自転車を漕いでいる姿が目撃されたとか(同, p. 15)。
ドノヴァン夫妻の娘ジャネットは、看護師になった。
3 両親クリストファー・アダムスは、グラスゴーの医者一族、アダムス家においてはいわゆる「不肖の息子」だった、と言えるかもしれない。医者にならなかったし、なろうともしなかったのだから。
クリストファーの子供時代は、今となってはよくわからない。父親のダグラス・キンチン・アダムスは仕事が忙しくて家族と過ごす時間はあまり多くなかったようだが、家庭放棄と言えるレベルのものだったかは定かではないし、息子であるクリストファーが医者にならなかったことへの失望をどの程度あからさまにしていたのかについても知りようがない。ただ、ダグラス・キンチン・アダムスとその妻は必ずしも円満ではなく、彼らの子供たちが不仲な両親の間で葛藤することはあったようだ。また、両親との関係だけでなく、クリストファーと実の姉妹であるポーリーンとの間にも不和があったようで、大人になってからは連絡を取り合うこともあまりなかったらしい。
クリストファーは、1949年にケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジに進学し、1951年に神学の学位を取得した。アダムスの母親、ジャネットと出会って結婚するのはこの時期である。にもかかわらず、というべきなのか、クリストファーはセント・ジョンズ・カレッジに続いて今度はケンブリッジ大学の中でも英国国教会の牧師の養成機関であるカレッジ、リドリー・ホールに進む。
だからと言って、クリストファーが本気で英国国教会の聖職者になることを目指していた訳でもなかったようだ。聖職者として仕事をしたいと願ったというより、聖職者の資格を持っておくことで社会的立場を確保できるという意味合いのほうが強かったのだろうか。Dont't Panic によると、友人たちにやめておけと説得されて聖職者になるのを断念した、とのことだが(p. 3)。
実際、クリストファーが神学に期待していたものは、手堅い職でもなければ篤い信仰心の発露でもなく、この世の仕組みや存在理由といったものを見出すことにあった。そしてその独特の探究心から、クリストファーは1950年代半ばにはスコットランド西部のヘブリディーズ諸島にあるアイオナ島を訪れることになる。
アイオナ島は、536年にアイルランドからやってきた修道士コロンバが修道院を創設し、キリスト教布教活動を積極的に行ったことから、スコットランドやアイルランド地域におけるキリスト教活動の中心地となった場所である。8世紀末から9世紀にかけてのヴァイキングの襲撃や、16世紀の宗教改革などの影響で、修道院はたびたび破壊されたが、そのつど修復・再建され、1938年に上院議員のジョージ・マクロードがキリスト教のコミュニティを起こしたことで、近年再び信仰の島としての注目を集めるようになっていた。
武部好伸著『スコットランド「ケルト」紀行 ヘブリディーズ諸島を歩く』によると、コロンバが修道院を設立した当初は、キリスト教はキリスト教でもいわゆるローマ・カトリックではなく、ドルイド教とキリスト教が融合したケルト教会だった。時代の変遷に伴って11世紀頃からカトリックへと移行し、「その後、豪族のレジナルドによってベネディクト教団の修道院が建てられ、ことごとくカトリック一色になってしまった。そして一六世紀に宗教革命が起こった。現在の修道院はカトリックの形をとりながらも、プロテスタント(プレスビテリアン)によって管理されるというじつに奇妙な形態をとっている」(p. 192)。
プレスビテリアンとは、スコットランドのプロテスタントに多い長老派のこと。とは言え、クリストファーが参加したアイオナ・コミュニティは、キリスト教の宗派の違いを乗り越えようという考えで設立されたものであり、純然たる長老派とは異なるようだ。おまけに、現在のアイオナ・コミュニティはむしろケルト教の復権の旗印になっているらしい。
クリストファーが参加していた当時、アイオナ・コミュニティが具体的にどのような宗教活動をしていたのかはよく分からない。が、同じプロテスタント系キリスト教徒の集まりだったとしても、それまで彼が過ごしていたケンブリッジ大学の英国国教会の牧師養成機関とは趣きはかなり異なっていたのではないか。あるいは、グラスゴーで生まれ育ったクリストファーにとっては、英国国教会より長老派のほうが実は馴染みがあったのかもしれない。ともあれクリストファーは、アイオナ島でいわゆる共同幻視のようなものを体験した。そして、その体験は到底散文では語り得ないということで、叙事詩を書いたらしいーー残念ながらその詩は現存していないけれど。
しかし、散文では語り得ないと言う割には、クリストファーはその体験について口をつぐんでいた訳ではなかった。それどころか、アイオナ島で一緒だったイアン・マッケンジー牧師いわく、当時のクリストファーはそのことばかり喋りまくっていたようだ。興味のあることについて周囲の人に話さずにはいられない辺りも、アダムスは父親とよく似ていたと言えるかもしれない。
ただし、そんな宗教体験を聞かされる妻ジャネットの心中は、決して穏やかではなかったのではないだろうか。アダムスの公式伝記には、クリストファーのアイオナ島行きは「1950年代半ば」としか書かれていないが、クリストファーとジャネットの二人が結婚したのは1951年、翌年の3月11日には長男ダグラス・ノエル・アダムスが誕生、さらにその3年後の1955年3月には長女スーザンが誕生している。「1950年代半ば」とは、ジャネットが第二子を懐妊中もしくは出産直後のことであり、そんな時期に宗教コミュニティに参加していても妻子が困らないほどに、クリストファーに経済的余裕があったとは考えにくい。
あくまで私個人の推測の域を出ないが、クリストファーの父、ダグラス・キンチン・アダムスが、不肖の息子はともかくとして、目の中に入れても痛くない大事な孫のために十分な金銭的援助を行っていた、とも思えない。というのも、ダグラス・キンチン・アダムスが亡くなったのは1967年のことだが、1952年生まれのアダムスは、生前の祖父に一度も会ったことがないと語っているからだ(Gaiman, p. 9)。アダムスが自分の父方の家系がスコットランドでは有名な医者の一族であることを知ったのは、大人になってからのことだという(Hitchhiker, p. 7)。交流どころか、没交渉もいいところだった、と考えたほうが良いのではないか。
実際のところ、一家の家計は苦しかった。
クリストファーには、四人家族の金銭問題をどうにか改善しようという意識はあまりなかった。家計の状態がどうであろうと、ダンヒルに好みのパイプ煙草の葉を注文することを止めなかったし、贅沢な食事をあきらめるつもりもなかった。収入の有無にかかわらず、そうすることがクリストファーの生活スタイルであり、一種のダンディズムだったのだろうが、ジャネットとしてはたまったものではなかったはずだ。
経済観念ゼロの夫と違い、ジャネットは地に足のついた人間だった。
クリストファーと出会った1951年当時、彼女はケンブリッジのアデンブルックス病院で看護師として働いていた。この病院は1766年に創設されたケンブリッジ大学付属の医療機関で、総合病院としてイギリスでも有数の規模を誇っている。1976年にヒルズ・ロードを南東に進んだケンブリッジ郊外の移転されたが、ジャネットが勤務していた頃までは母体であるセントキャサリン・カレッジに近いケンブリッジ中心部、トランピントン・ストリートにあった(現在、病院の跡地にはケンブリッジの経営大学院、ジャッジ・ビジネス・スクールが建っている)。
ジャネットは、クリストファーと出会ってすぐに恋に落ち、ケンブリッジシャーのウィスベックで結婚した。結婚を機にジャネットがアデンブルックス病院を退職したかどうかは定かではない。当時のクリストファーがまだ学生だったことを思えば、結婚後も働き続けた可能性はゼロではないが、結婚の翌年には第一子であるアダムスを出産しているくらいだから、たとえジャネットが看護師として働いていたとしても、その収入だけで子供を養い、かつクリストファーの贅沢な生活を支えることはほとんど不可能だったのではないか。事実、アダムスが生まれた約6ヶ月後には一家はケンブリッジを離れ、その後は東ロンドン周辺を転々とすることになる。そのような暮らしの中で、1955年3月、アダムスの3歳年下の妹、スーザンが誕生した。公式伝記によると、この頃には既に夫婦の関係は緊張状態にあったようだが、クリストファーとジャネットが正式に離婚に至るのはそれから2年後のことである。
4 幼年期アダムスには、幼い頃の思い出があまりないという。「子供というのは、自分たちの生活がまともなのだと無理にでも思いたがるものだ。もちろん、簡単なことではないけれど。僕の両親が離婚した当時、今と違って離婚はおよそ一般的なことではなかったし、正直言って僕には5歳以前の記憶がほとんどないんだ。何にせよ、楽しい日々ではなかったんだろうね」(The Salmon of Doubt, p. xvii)。
不安定な家庭環境の影響があったかどうかはさておき、アダムスは言葉を話し始めるのがとても遅かった。公式伝記によると4歳まで喋らなかったという。母親のジャネットも、検査のために病院に連れて行った事実は認めている。診察した医師は、勿論、問題なしと診断した。
アダムスが5歳の時に両親は離婚、アダムスは3歳年下の妹スーザンと共にジャネットに引き取られ、エセックス州ブレントウッドにあるジャネットの実家に移り住む。
そこはエドワード朝に建てられた当時のままの陰気な内装の家で、アダムスにとっては母方の祖父にあたるミスター・ドノヴァンは病気で寝たきりだった。アダムスとスーザンは、一つ屋根の下で暮らしていながら祖父に会うことは滅多になかったという。後にスーザンは、祖父の寝室は暗い廊下の突き当たりにあり、そのドアは祖父が死ぬまでずっと閉じたままだったと回想している。
一方、RSPCA(王立動物虐待防止協会)の熱心な活動家だった祖母のミセス・ドノヴァンは、飼えなくなったペットや怪我をした野生動物をケアするため、自宅を RSPCA の公式な保護施設として開放していた。その結果、幼いアダムスが暮らす家は常に怪我をした動物たちでいっぱいだったが、子供の頃から動物と身近に触れ合うことでアダムスが動物好きとなったかと言えばさにあらず、というからおもしろい。それどころか、決して衛生的とは言えない自宅環境(台所のような場所ですら、鳩が飼われていたらしい)のせいで喘息とアレルギーを引き起こすことになった。
アダムスは、"My Nose" というタイトルのエッセイの中で、「母親の長い鼻と父親の幅広の鼻を受け継いだせいで、自分の鼻は巨大になった」(The Salmon of Doubt, p. 12)と嘆いた後、このアレルギー性鼻炎は、アダムスが祖母の家を出てブレントウッド・スクールの寄宿舎に移った途端に症状が治まったそうで、これでは動物好きになるほうが難しい。1994年発表のエッセイ "Maggie and Trudie" で、アダムスが「これまで一度も犬を飼ったことがない」(同、p. 16)と書いているのも頷ける。私の鼻のさらなる奇妙な特徴が、空気を通さないことだ。理解しがたい、信じがたいことではある。この問題ははるか昔、子供だった私が祖母の家で暮らしていた頃に遡らなければならない。祖母は王立動物虐待防止協会の地方代表で、そのため家にはいつもひどい怪我をした犬や猫、時にはアナグマやオコジョや鳩までいた。
そういった動物たちは、身体の傷だけでなく心の傷を負っているものもいたが、彼らのせいで私は長い時間集中することができなくなった。というのも、家の中の空気が動物の毛やホコリでいっぱいだったため、私の鼻は炎症を起こして鼻水が止まらなくなり、15秒ごとにくしゃみをする羽目になったからだ。どんな考えも、15秒以内にまとめたり深めたり論理的結論にたどりつかない限り、大量の粘液と共に頭から強制排除させられてしまった(同、p. 13)。一方、母親のジャネットは、地元の病院で看護師として働いていた。昼間に子供たちと一緒にいられるようにと、なるべく夜勤中心のシフトを選んだというから頭が下がる。とは言え、ここで一つ疑問が出てくる。いくら給与面で厚遇されるであろう夜勤中心だったとしても、母親の看護師としての収入だけで、ブレントウッド・スクールのような授業料の高いパブリック・スクール(私立校)に息子を通わせることができるのか?
イギリスのパブリック・スクールの授業料の高さは、日本の私立校の比ではない。寄宿制だからということもあるが、自宅通学が許されたとしても、対ポンドのレートにも依るとは言え最低でも日本円にして二、三百万円はかかる。一方、イギリスの看護師の社会的地位や収入は、仕事の大変さや大切さの割にはそう高くはないはずだ。無論、イギリスの看護師が実は日本の看護師事情とは似ても似つかぬ高給取りだ、という可能性もゼロではないが、だとしたらジャネットの贅沢好きの元夫が少しくらい放蕩したところで家計が逼迫することもなかっただろう。
それ故、私が1988年に初めてニール・ゲイマンの Don't Panic を読んだ時、アダムスが通ったというブレントウッド・スクールは、パブリック・スクールではなく地元の優秀なグラマー・スクールだと思って疑いもしなかった(新潮文庫『宇宙の果てのレストラン』の訳者による解説には「エセックス州のブレントン校で教育を受け、大学はケンブリッジのセント・ジョン・カレッジだった」と書かれているが、"Brentwood" は「ブレントン」とは発音しないと思う)。後に、インターネットというものが素人にも簡単に使える時代になってから、Brentwood School をネット検索し、ブレントウッド・スクールがれっきとしたパブリック・スクールの一つであることを知って驚くと同時に、首をかしげた。
幸いと言おうか何と言おうか、そういう下世話なことを考えたのは私だけではなかった。アダムスの公式伝記を読むと、著者も同じ疑問を抱いていたらしい。そして、疑問に思ったまま放置していた私と違い、その答えを見つけ出した。
アダムスの教育費を賄ったのは、父クリストファーの再婚相手の女性だった。
5 義母の家系(父の再婚相手)1960年7月、アダムスの父クリストファーは、メアリー・ジュディス・スチュワートという未亡人と再婚した。
メアリー・ジュディス・スチュワートの旧姓はジュディス・ロバートソン。スコットランド南部クライド川沿いで造船業を営む裕福な一族に生まれた。が、実の母親を7歳の時に亡くし、父親も18際の時に亡くしている。その後、義兄弟で英国空軍士官だったアリステア・マクリーン・ベアードモア・スチュワートと最初の結婚をし、ローズマリーとカリーナという二人の娘に恵まれたが、1944年、夫はノルウェイへと向かう任務で死亡した。
公式伝記によると、クリストファーと再婚した後のジュディスは実家とはどんどん疎遠になっていったという。両親が既に死亡しているとあっては、無理もないことだったかもしれない。とは言え、ジュディスの財政的豊かさは彼女の出自に依るものであり、また、クリストファーの財政的基盤は再婚相手の資産に依るものだったのも、否定しがたい事実ではある。
クリストファーにとっては義理の娘にあたるローズマリーは、母親は完全にクリストファーに支配されていると感じ、「ママはクリストファーの玄関マットだった」(Webb, p. 39)とコメントしている。実際、ローズマリーが二人の再婚を知らされたのも、当時寄宿学校に入っていた彼女の元を不意に母親が訪ねてきた時のことだった。コテージに行くからと、ローズマリーと妹のカリーナが母親に学校の外に連れ出されると、車には見知らぬ大きな男の人が乗っていて、コテージに着いたところで母親からあの男性と結婚したと打ち明けられたのだとか。
母親の再婚などまったく寝耳に水だったローズマリーは、当然ながら強いショックを受けた。彼女が気持ちの整理をつけて事実を受け入れることができるようになったのは、大人になってからのことだったという。
一方、妹のカリーナは、ローズマリーほどのショックを受けなかった。父アリステアが戦死してから生まれたため、実父の記憶がないことも幸いしたのかもしれない。カリーナは、「10代の頃のことは頭に霞がかかったみたいでよく思い出せない」(同, p. 39)としながらも、当時拒食症を患っていた彼女が気分が落ち込んでいると、クリストファーが何時間でも話を聞いてくれた、と語っている。
結局のところ、義父と二人の娘の関係は、険悪ではないとしても微妙なものではあったようだ。ローズマリーもカリーナも寄宿学校に入っていたため、学校の長期休みを除けば義父と毎日顔を合わせる必要がなかったのは、お互いにとって好都合だったにちがいない。ニック・ウェブに言わせれば、「娘たちが二人とも若くして結婚し、家を離れたのは、多分偶然ではない」(同, p. 39)。クリストファーとジュディスは、結婚後、エセックス州にある Stondon Massey という風光明媚な村に引っ越した。それだけなら、単に新婚夫婦が自分たちの暮らしを始めるために新しい家に移り住んだだけのように思えるが、実はこの村、アダムスが祖父母たちと暮らしているブレントウッド北部に位置していて、ブレントウッドからは20キロと離れていない。実際、村から車で行ける最寄り駅はブレントウッドだった。
クリストファーとジュディスの新居は、「デリー(Derry)」と呼ばれるテューダー様式を模した美しい館で、広い庭やテニスコートもあった。ニック・ウェブは、いくらでも好きな場所に住める財力があるのにわざわざ前妻たちのすぐ近くに引っ越したのは不思議だと書いている(同, p. 40)。が、この先ジュディスがクリストファーと前妻の間に生まれた二人の子供の教育費まで快く負担したことを考えれば、不思議でも何でもないのではないか。引っ越し先について、クリストファーとジュディスのどちらが最初に提案したのかは不明だが、彼らはアダムスとスーザンに対しても親としての責務を果たすべきと考えたのだろう。
とは言え、いくら裕福だったとしても、誰もが自分とは何の血のつながりもない前妻との間に生まれた子供のために高額の教育費を気前よく払えるものではない。ジュディスには既にローズマリーとカリーナという二人の娘がいて、その上、1962年にはクリストファーとの間にヘザーという娘が誕生しているのだから。ローズマリーは母親のことを「品格のある人(decent person)」(同, p. 42)と表現しているが、実際その通りだったにちがいない。ジュディスは、5人の子供たち全員のために信託基金を作り、クリストファーの友人を管財人の一人にした。
かくして、アダムスはブレントウッド・スクールへ、妹のスーザンはフェリクストウ・カレッジに進学することができた(後にヘザーも、スーザンと同じフェリクストウ・カレッジに入っている)。
ジュディスも内心は複雑だったかもしれないが、前妻のジャネットやその両親であるドノヴァン夫妻の心中はさらに複雑だったにちがいない。ジャネットは、意地で教育費の援助を断るほど非実際的な性格ではなかったようだが、アダムスとスーザンは、単にジュディスに授業料を払ってもらっただけではなかった。週末ごとに、二人はクリストファーとジュディスが暮らす「デリー」を訪れるようになったのだから。
一方は、ブレントウッド市街にある、古くて陰気な、怪我をした動物だらけの家。母親は看護師で、夜勤シフトを多めに入れている。もう一方は、エセックス州でも指折りの景観で知られた美しい村にある、美しい館。そこで暮らす父親は、仕事らしい仕事をしている風でもなく、再婚相手に買ってもらった高級車を乗り回している。この二つの家を、二つの環境を、もっと言えば二つの階級を、週末ごとにアダムスとスーザンは行き来したのだ。
余計な想像かもしれない。でも、想像せずにはいられない。恐らく、このデリーで過ごした時間がアダムスに贅沢の味を教えたにちがいない、と。カリーナは、ジュディスがクリストファーとアダムスの二人が良く似ていると言ったことがあるというが、クリストファーにしてもアダムスにしても、いわゆる「清貧の思想」は持ち合わせていなかった。
勿論、再婚相手の財力に依存していた父親と違い、『銀河ヒッチハイク・ガイド』以降のアダムスには、少々の浪費を許すだけの経済的ゆとりがあった。それに、アダムスは自分のためだけでなく、友達や親しい人のためにも気前よく大盤振る舞いした。そういう意味では何の問題もないのだが、しかし、ここから先はあくまで私の邪推であることを断った上で、敢えて言おう。やはりクリストファーとアダムスは、単に贅沢好きというだけでなく、お金に関する感覚とか考え方が根本的なところでよく似ていたのではないか。
一言で言えば、お金に関して卑屈にならない。
再婚相手に高級車をねだるクリストファーの心理は、正直に言って私には理解しがたい。が、きっとグラスゴーの有名医師の息子として生まれ、ケンブリッジ大学を卒業したクリストファーは、自分にはそういう車がふさわしいと信じて疑いもしなかったのだろうと思う。金の有る無しや、金の出所はあまり問題ではないのだ。
一方のアダムスは、30歳を前に『銀河ヒッチハイク・ガイド』で大金を手にした途端、それまで共に貧乏暮らしをしてきたコメディ作家やプロデューサーの友人たちに対してあまりに露骨に成功者然として振る舞ったせいで、仲間たちの気を悪くさせることがあったらしい。無神経というより、奢られることで卑屈な気持ちになるなんて想像だにしないのだろう。要は、自分が逆の立場だったとしても奢られることにあまり不快を感じないから、ということなのかもしれないが、それだけではない。ライターの仕事がなく金が尽きた挙げ句に友人のフラットに転がり込むような状態だった時に、突然やってきた『銀河ヒッチハイク・ガイド』という逆転満塁ホームランに対して、自分にはそういう成功こそがふさわしいと信じて疑いもしなかったのではないか。
ラジオ・ドラマ『銀河ヒッチハイク・ガイド』は、紛れもなくダグラス・アダムス作品だ。だが、脚本をドラマに仕上げてくれたのはプロデューサーのジェフリー・パーキンスであり、ネタに詰まった第5・6話目の執筆を助けてくれたのはジョン・ロイドである。アダムスだってこの二人には心から感謝していただろう。だが、アダムスの感謝は、謙虚さには決して繋がらない。謙虚は時として卑屈に通じることがあるが、謙虚にならないアダムスはどう転んでも卑屈にならない。手にした大金は、あくまで自分にふさわしいものなのだ(その結果、後にアダムスはパーキンスとロイドに対し、私に言わせればいささか失礼な行動に出るが、それはまだ先の話)。
贅沢な暮らしに、本人の実力や実績が伴っていたかどうかの決定的な違いはある。が、妻の資産で贅沢するクリストファーと『銀河ヒッチハイク・ガイド』の印税で贅沢するアダムス、私には二人が意外によく似ていたような気がしてならない。話を戻して、幼い二人をデリーに連れて行ったのは、クリストファーとは顔も合わせたくない母親のジャネットではなく、祖母のミセス・ドノヴァンだった。クリストファーとジャネットの冷戦状態はその後も続いたが、彼女とジュディスは良好な関係を築けたようだ。
ただし、肝心のアダムスと父クリストファーとの関係は、単純に「良好」とはいかなかった。父と子は、学校が休みの週末ごとに会い、たまには一緒にヨーロッパにドライブに出かけたりもしたらしい。ウィーンで行われたジェルジ・リゲティの講義に行ったのも、その一例だった。にもかかわらず、直接的に言葉には出されないものの、二人の間には不穏な緊張感があって、アダムスの義妹ヘザーもそれは察していたという。アダムスの妻ジェーン・ベルソンも、アダムスは子供の頃に実父から褒めてもらったり肯定的な言葉をかけてもらえなかったことについて心にひっかかるものを持っていたと語っている(当時のイギリスでは、子供を褒めて育てるという考え方はあまり一般的でなかったのも事実だが)。
とは言え、クリストファーは子供相手に話をするのは苦手ではなかったはずだ。先に書いた通り義理の娘カリーナの相談相手になってやったこともあるし、少年院に入っている子供たちと話をするのも巧かったらしい。その特技をいかして地元の保護観察官を務めていたこともある。ニック・ウェブいわく、クリストファーにとってその地区でただ一人の、高級車アストン・マーティンを乗り回す保護観察官、というキャラクター設定はまんざらでもなかったようだ(p. 40)。また、ご先祖同様に人前でスピーチをするのも得意で、後には「経営コンサルタント」の肩書きで講演することもあった——アダムスに言わせれば、「父とマネジメントという言葉くらい、相容れないものもない」ということだけれども(同、p. 37)。さて、後にアダムスが『宇宙の果てのレストラン』の中で、ゴルガフリンチャム箱船船団B号船に「経営コンサルタント」を乗船させたのは、どこまで実父を意識してのことだったのだろうか?
1985年6月、クリストファーは家族に看取られてドロイトウィッチ病院(Droitwich Hospital)で亡くなった。アダムスは、義母ジュディスからの連絡を受けてクリストファーが亡くなる前夜にアメリカから駆けつけたが、家族が交代で容態を見守っている中で、たまたまアダムスが休憩の順番になって席を外したタイミングで息を引き取った。アダムスはひどく気落ちして、「いかにも父らしい。僕がいなくなるのを待って死ぬなんて」と語ったという。
ドロイトウィッチはコッツウォルズ地方の近くにある町で、インターネットで検索してみた限りでは、2011年現在、'Droitwich Hospital'という名称の病院は見つからなかった。「ドロイトウィッチ」の地名がつく唯一の病院は BMI The Droitwich Spa Hospital で、「スパ」という名称から想像する通りの高級感あふれる私立病院である。ここなら、クリストファー・アダムスが入院していたとしても不思議ではないと思う。
なお、クリストファーの死から5年後に出版された、アダムスとジョン・ロイドの共著による地名遊びの本 The Deeper Meaning of Life には、他ならぬ「ドロイトウィッチ」の定義もある。ストリート・ダンスの一種。二人のパートナーが反対方向から近づいてきて、お互いに相手に道を譲ろうとするが、二人とも左側に避けて、今度は右側に避け、謝罪し、また揃って左に避け、ごつんと頭をぶつけ合い、この一連の動作を不必要なまでに繰り返す(p.31)。
1964年7月、アダムスの母ジャネットは、獣医師ロン・スリフトと再婚した。この結婚を機に、アダムスと妹のスーザンは祖母の家からそれぞれの学校に通学していたのを止め、学校の寮に入ることになる。ロン・スリフトがドーセット州シャフツベリーに新しい動物病院を開業することになると、ジャネットもロンと共にシャフツベリーに引っ越した。1966年8月にはアダムスにとっては種違いの妹になるジェーンが、1968年には種違いの弟となるジェイムズが誕生する。
と書くと、何だかアダムスと妹スーザンはロン・スリフトに実母を奪われてしまったかのような印象を与えかねないが、実際のところ、アダムスと義父ロンとの関係は生涯に亘ってとても良好だった。実父との関係よりもよほど、と言っていいかもしれない。魅力的ではあっても気難しい実父クリストファーに対し、義父のロンは誰からも愛され、尊敬されるタイプの人間だった。ジャネットとの間にジェーンとジェイムズという二人の実子が産まれてからも、アダムスやスーザンにできる限りのことはしたという。
1991年、ロンはガンのため59歳の若さで死去した。アダムスは、1985年に実父が亡くなった時よりも強い悲しみを感じたらしい。1992年に発売された小説『銀河ヒッチハイク・ガイド』シリーズ5作目『ほとんど無害』の献辞に出てくる「ロン」とは、この義父のことである。
アダムスは、義父だけでなく、種違いの兄弟二人とも親しく交流していた。姉のジェーンについては、後に、アダムスがジェーン・ベルソンと結婚してからは、彼女は身内の間では二人を区別するためにリトル・ジェーンと呼ばれるようになった。アダムスは、兄としてまたは保護者として親身にしていたようだ。実際、アダムス夫妻が暮らしていたイズリントンの豪華なフラットには、リトル・ジェーン用の部屋もあったという。
アダムスが妹思いなのはともかくとして、小姑との同居を迷わず受け入れたビッグ・ジェーンの度量には感心する。だが、アダムスの公式伝記には、アダムスの善意が時としてリトル・ジェーンを不要に傷つけることもあったのではないかと思われるエピソードも書かれている。
アダムスは、たびたび自宅に親しい友人を招いてパーティを開いていた。ただ、この「親しい友人」というのが大抵は有名なメディア関係者だったのが普通の自宅パーティとは異なるところで、ある日、看護師の仕事を終えて制服姿のまま帰宅したリトル・ジェーンに、ちょうどパーティが終わってコーヒーを飲んでいるところだったアダムスの「親しい友人」の一人、ジョン・カンターがこう声をかけたという。「やあジェーン、一体いつになったらちゃんとした仕事に就くんだい?」(p. 43)。
リトル・ジェーンは、母親ジャネットと同じ看護師の道を選んだ。が、看護師としての訓練を受ける決意を固めるまでには、身近にいるアダムスの影響で、名もなき一介の看護師ではなく、何かもっと凄いこと、素晴らしい仕事ができるのではないかという気持ちもあって、それなりの紆余曲折があったようだ。勿論、アダムスにしても、リトル・ジェーンが母親と同じ看護師になることに反対はしなかっただろう。でも、イズリントンの一等地に妹を一緒に住まわせていた時、アダムスは彼女に看護師になる以上のものを期待していなかっただろうか。
ただの看護師なんて、ちゃんとした仕事(a real job)じゃない。アダムスの自宅に招かれるようなメディアエリートたちにとって、ジョン・カンターの言葉はジョークであってジョークではない。私がリトル・ジェーンの立場だったら、良いも悪いもそういう価値観がまかり通る(種違いの)兄の家に居続けるのは時としてちょっとキツいのではないかと思うのだが。
リトル・ジェーンの弟、ジェイムズについては、公式伝記にはブロンウェンという女性と結婚し、イギリス南西部でビジネスをしている、と書かれている。彼のツイッターIDから探ってみたところ、生まれ育ったシャフツベリーでアップル・コンピュータの使い方指導やメンテナンスサービスの店(The Dorset Mac Man)を運営しているらしい。彼はアダムス亡き後、アダムスの著作権管理も担当していて、アダムスが脚本を書いた『ドクター・フー』 'The Pirete Planet' のDVDの特典映像には、公式伝記の作家ニック・ウェブと一緒に登場している。また、2004年8月に『銀河ヒッチハイク・ガイド』がロンドンで撮影された時には、母親のジャネットを筆頭に実の妹のスーザン、リトル・ジェーンとジェイムズ&ブロンウェル・スリフトらと共にロケ地を訪れている。
ブレントウッド・スクール時代のアダムスについては、M・J・シンプソンの非公式伝記にかなり詳しく書かれている。故に、この章の内容はその多くをこの非公式伝記に依っている。が、イギリスの教育制度は日本と比べてかなり複雑で、公立と私立では進学する年齢も名称も異なる上、学期の呼び名までややこしい。正直に言って、当時のブレントウッド・スクールの教育システムを自分がきちんと把握できているか心もとないので、敢えてM・J・シンプソン程には細部に亘って紹介しないことにする。もっと詳しいことや正確なことが知りたい方は、非公式伝記を直接手に取っていただきたい。
アダムスは、ブレントウッドの街中にあったプリムローズ・ヒル小学校(Primrose Hill Primary)に通っていた。が、6歳の時にブレントウッド・スクールの面接を受けて合格し、1959年9月、晴れてブレントウッド・スクールに入学する。以来、1970年12月に卒業するまでの11年間を、このパブリック・スクールで過ごした。
ブレントウッド・スクールは、イギリスの典型的なパブリック・スクールの一つである。広大な敷地と由緒ある建築物。級長制度や寮制度。ラグビーに冷たいシャワー。そして勿論、高額な授業料。これを支払ったのは、先に書いた通り、アダムスにとっては義理の母にあたるジュディスである。
1959年にアダムスが入ったのは、ブレントウッド・スクールの中の「プレパラトリー・スクール」にあたる。プレパラトリー・スクールとは、パブリック・スクールに進学するための初等学校のこと。アダムスはプレパラトリー・スクールに4年間在籍した後、「シニア・スクール」に進学した。
入学当初、アダムスは母方の祖母の実家から自宅通学していた。が、母ジャネットがロン・スリフトとの再婚に伴い引っ越しすることになったのを機に、学校の寮に入ることになる。ジャネットいわく、アダムスのは母親の再婚話を聞かされたとき、転校させられると思って大泣きしたそうだ。が、寮に入れば転校しなくて済むと分かると、ぴたっと泣き止んだという。
それほどまでに、アダムスはブレントウッド・スクールを気に入っていたのだろうか。ニール・ゲイマンの Don't Panic には、球技がヘタだったせいで学校生活に良い思い出があまりない、とも書かれているが。アダムスいわく、「ラグビーは死ぬほどヘタくそだった。初めてプレイした時に、自分の膝で自分の鼻の骨を折ったんだ」(p. 4)。
アダムスの学校生活における不幸な思い出と言えば、半ズボンの制服にまつわる話を無視することはできない。学校の規則でプレパラトリー・スクールの生徒は半ズボンの制服を着ることになっていたが、子供の頃から飛び抜けて背が高かったアダムスの半ズボン姿はひどく不体裁だった。やっとメイン・スクールに進むことになり、授業開始前の夏休みに長ズボンの制服を買いに行ったところ、あまりに背が高いアダムスのサイズに合う既製品がなくて特注することになる。が、問題は、シニア・スクールの授業は4週間後に始まるのに、特注した長ズボンが出来上がるのに6週間かかると言われたこと。つまり、他の同級生たちは長ズボン姿で登校してくるのに、アダムスだけは最初の2週間を半ズボン姿で過ごさなければならなくなったのだ。この出来事については、アダムス自身が The Salmon of Doubt に収録されているエッセイ "Brentwood School" で詳しく書いているので、是非ご参照あれ。
勿論、プレパラトリー・スクール時代にも良い思い出となる出来事はあった。その最たるものは、恩師フランク・ハルフォードとの出会いであろう。ハルフォードは英語とフランス語の教師だったが、1962年3月7日、英作文の授業でハルフォードはアダムスが書いたショートストーリーに10点満点を付けた。
たかが小学校の作文と言うなかれ。ハルフォードの32年の教師生活において、10点満点をつけたのは後にも先にもアダムスただ一人だったのだから。アダムスの後輩にあたる生徒たちが、自分の作文が9点なのはおかしい、先生は誰にも満点をつけないんじゃないですかと文句を言いに来ると、ハルフォードは決まってこう答えたという。「そんなことはないよ。前に、ダグラス・アダムスって名前の少年に満点をあげたっけ」(Hitchhiker, p. 10)。
このことは、アダムスがプロの作家になった後までも彼に自信を与え続けた。「作家の壁にぶちあたり、まあほとんどいつもそうなんだけど、ほーっと座っているだけでこれ以上もう何も考えつかないと思った時、「そうだ、僕はかつて10点満点を取ったことがあったじゃないか!」と思う。ある意味、あの本が百万部売れたとか、この本も百万部を突破したとかいうより、ずっと大きな励ましになる」(Don't Panic, p. 5)。
1992年7月、プレパラトリー・スクール創立記念のスピーチ大会のゲストとして招待されたアダムスは、ハルフォードと再会した。1995年6月24日には、アダムスの愛娘ポリーの(非宗教的な)洗礼式に恩師を招待している。
1998年には、「有名人とその恩師」という趣旨で、アダムスとハルフォードはそれぞれデイリー・メールの取材を受けた。このインタビュー記事の中で、ハルフォードは生徒だった頃のアダムスについて、「不自然なまでに背が高いのに半ズボンをはかされていたせいで、少しばかり自意識過剰になっているように見えた。でも、何より彼を輝かせていたのは、第一級のストーリーを書く才能だ。気さくで利発な少年だったと記憶しているが、英語に天賦の才があることはすぐに分かった」(The Dairy Mail, 7 March 1998, p. 24)と語っている。
ハルフォードは、アダムスが1963年に寮のクリスマスパーティのために書いた寸劇の脚本にも感銘を受けたという。その寸劇のタイトルは、『ドクター・フィッチ(Doctor Which)』。言わずと知れた、『ドクター・フー(Doctor Who)』のパロディである。『ドクター・フー』のテレビ放送が始まったのは、同年11月23日。土曜日になると、寮の生徒たちは一つしかないテレビでこの番組を観ることが許可されていた。さすがのハルフォードも、このパロディ寸劇の脚本を書いた11歳の少年が後に本物の『ドクター・フー』の脚本編集者になるとまでは思わなかったが、はっきりと記憶に残る出来事だったらしい。
なお、M・J・シンプソンは、非公式自伝 Hitchhiker で、この脚本が書かれたのは1964年だと主張している。それに対し、2009年に Nicolas Botti が行ったインタビューの中で、ハルフォードはあくまでこれはアダムスが11歳の時のクリスマスパーティだったと反論し、逆にM・J・シンプソンの間違いを指摘した。シンプソンの非公式伝記には、アダムスは最初に Barnards という名前の寮に入り、この寮のクリスマスパーティで『ドクター・フィッチ(Doctor Which)』を披露し、後に Otway という名前の寮に移った、と書かれているが、ハルフォードいわく、Otway はプレパラトリー・スクールの生徒のための寮で、アダムスが最初から Otway に入り、メイン・スクールに進学するにあたって「スクール・ハウス」に移ったとのこと。Barnards という名前の建物はあるけれど、そこは寮ではなかった、とも。
ただし、(後述する)アダムスの1964年の成績表には、"House Barnards" と明記されている。故に、ハルフォードの言葉を鵜呑みにしてM・J・シンプソンが間違っていると断言することもできない。
話を戻して、子供の頃のアダムスの文章力を評価したのは、ハルフォードだけではなかった。1965年1月23日付で発売された子供向けのSF雑誌 Eagle には、12歳のアダムスが投稿した手紙が掲載されている(ゲイマンの Don't Panic には「11歳の時」(p. 5)と書かれているが、これは間違い)。初めて活字になった、という意味で記念すべきこの文章は、The Salmon of Doubt に転載されているので、今では簡単に読むことができる。
続いて2月27日付の号には、ショートストーリーが採用された。このショートストーリーのほうは、ゲイマンの Don't Panic 内で読むことができる(p. 6)。The Salmon of Doubt と違い、テキストだけでなく当時の誌面そのものが転載されているため、さらに感興深い。
授業での作文や商業雑誌への投稿の他に、アダムスは別の学校で寮生活を送る妹のスーザンに定期的に手紙を書いていた。この手紙があまりにおもしろかったため、スーザンが自分の学校友達に披露したところ、彼女の友達までアダムスの手紙のファンになり、みんなで彼からの手紙が着くのを心待ちにしていたという。残念ながら、これらの手紙は現存していない(Webb, p.55)。
が、その割には、恐らくもっとも投稿しやすかったであろうはずのブレントウッド・スクールの学内誌 Brentwoodian には、アダムスの書いた文章はほとんど見当たらない。せいぜい、学校内の教会で祭具係やコーラス隊を務めたときのレポート記事くらいのものだ。その理由について、大人になってからのアダムスはこう語る。「何年か前に、昔の学内誌を目にする機会があったので、ページをめくって当時の自分が書いた記事を探してみた。が、自分の文章がちっとも見つからない。おかしいなあと首をひねった挙げ句、思い出したんだ。何か書こうとトライしても、いつも締め切りから2週間も過ぎてしまっていたことを」(Gaiman, p. 7)。
生徒たちが自主的にガリ版刷りで作った Broadsheet という雑誌には、無事に原稿の締め切りに間に合った数少ない文章の一つが掲載されている。ハムレットとオリバー・トゥイストとの対話、というパロディ。が、ここで注目すべきは、アダムスの文章そのものよりもこの雑誌の編集を担当した少年の名前だ。ポール・ジョンストン——後に、アダムスが『銀河ヒッチハイク・ガイド』の中で「宇宙一ひどい詩人」と呼ぶ、「ポーラ・ナンシイ・ミルストーン・ジェニングス」は、彼の名前をもじってつけられた。最初にラジオ・ドラマ版『銀河ヒッチハイク・ガイド』が放送された時は、彼の本名がそのまま使われていたらしいが、さすがにそれはマズいと判断されたのだろう。が、「ポーラ・ナンシイ・ミルストーン・ジェニングス」名で小説版が出版されてから、ポール・ジョンストンはパン・ブックスに苦情の手紙を書いている。
ポール・ジョンストンの他に、当時仲良くしていたスティーヴン・プロッサーという生徒も、『銀河ヒッチハイク・ガイド』の冒頭に出てくる市の職員、ミスター・プロッサーとして名前を使われた。幸い、スティーヴン・プロッサーからのクレームはなかったようだが。アダムスは、子供の頃から漠然と「作家になれたらいいな」という気持ちは抱いていた。SF雑誌 Eagle に連載されているコミックスや放送が始まったばかりの『ドクター・フー』に夢中になり、A・E・ヴァン・ヴォクトの『宇宙船ビーグル号』やE・C・エリオットの『宇宙少年ケムロ』を愛読していた。
が、そういったジュヴナイルSF以外に、あるいは以上に、少年時代のアダムスに強い影響を与えたものが二つある。
ビートルズとモンティ・パイソン。
The Salmon of Doubt に収録されたエッセイ、"The Voices of All Our Yesterdays" を読むと、アダムスが生涯に亘って抱き続けたビートルズへの思い入れの深さがよく分かる。1964年3月20日、学校を抜け出してビートルズの「キャント・バイ・ミー・ラヴ」を買いに行ったこと、レコードプレイヤーのある寮母の部屋に侵入して立て続けに3回聴いたところで捕まって罰を受けたこと。ギターを独学で練習し、かなりのレベルにまで上達する——42歳の誕生プレゼントとして、ピンク・フロイドのコンサートでソロ演奏をさせてもらえるほどに。
独学したギター演奏とは別に、ピアノは以前から正式に習っていたが、こちらはあまり続かなかったようだ。ちなみに、この時アダムスが習っていたピアノの先生は、アダムスより4歳年下の後輩、ポール・'ウィックス'・ウィッケンズも教えていた。アダムスと違い、ピアノを続けたウィッケンズは、後にポール・マッカートニーのバンドでキーボードを担当することになる。
非公式伝記 Hitchhiker によると、1969年、ブレントウッド・スクールの聖歌隊のメンバーだったアダムスは、教会でビートルズを歌わせてくれるよう大人たちを説得し、実行した。この時、ギターを弾きながら歌ったのが、アルバム『ザ・ビートルズ』(1968年)に収録されている「ブラックバード」。案の定(?)、多くの人の顰蹙を買う結果に終わったらしいが(p. 15)。ビートルズおよび音楽全般への愛は、アダムスの生涯に亘る趣味となった。一方、モンティ・パイソンとの出会いは、アダムスの職業を決定づけることになる。
1966年3月10日、風刺コメディ番組『フロスト・レポート』の放送が始まった。この番組に出ていたジョン・クリーズを見て、アダムスは将来こういう仕事をしたいと強く願ったという。
アダムスは、ブレントウッドの聖歌隊で歌ったり、学校劇に出演したりすることも多かった。将来の夢として、作家とか物理学者とかミュージシャンとか、ぼんやりと「なれたらいいな」と思うこともあった。そんなアダムスにとって、ライター兼パフォーマーとして活躍しているジョン・クリーズの姿は、ものを書くことと人前で演じることの両方を同時に実現できるという意味で、将来の理想像となった。
1969年10月5日から『空飛ぶモンティ・パイソン』が始まると、アダムスは熱狂的なファンとなった。勿論、当時この番組にはブレントウッドの多くの生徒が夢中になり、放送時間になれば寮のテレビの前に集まっていたのだが、第2シリーズが始まる頃になると、他の生徒たちの関心がサッカー中継に移り始める。アダムスいわく、「他の寮生たちが『空飛ぶモンティ・パイソン』ではなくサッカーの試合を観るつもりでいることが明らかになり、このままだと『空飛ぶモンティ・パイソン』を見逃してしまうと分かった僕たち四人は完全にパニックになった。僕の祖母が2マイル(約3.2キロ)離れたところに住んでいたので、僕らは学校を脱け出し、記録的な早さで走りに走って祖母の家に飛び込み、びっくり仰天している祖母に「ごめん、僕らは『空飛ぶモンティ・パイソン』を観なくちゃならないんだ」と言った」(Hitchhiker, p. 23)。
アダムスがブレントウッド・スクールからケンブリッジ大学に進学することに決めたのも、ひとえにモンティ・パイソン、中でもジョン・クリーズのようなライター兼パフォーマーになるにはそれが一番の近道だと考えたからだった。
単に、敬愛するジョン・クリーズがケンブリッジ大学卒だから、というだけではない。実際問題として、当時、イギリスの主なコメディ番組では、製作者も出演者もオックスブリッジの卒業生が多数を占めていた。中でも、ケンブリッジ大学の由緒あるコメディー・サークル「フットライツ」は、前述の『フロスト・レポート』で司会を務めていたデイヴィッド・フロストがこのサークルの卒業生だったこともあって、有望な若い書き手や出演者をサークルの後輩の中から探すことも多かった。他でもないジョン・クリーズもその一人である。フロストに続き、今度はジョン・クリーズが、フットライツの同輩グレアム・チャップマンに加え、後輩にあたるエリック・アイドルも引き込んで「モンティ・パイソン」を結成したのだから、アダムスが「ライター兼パフォーマーになるなら、まずはケンブリッジ大学に行ってフットライツに参加すべし」と考えたのは、極めてまっとうな戦略だった。志望動機が何であろうと、ケンブリッジ大学に進学するためには成績が良くなくてはいけない。
1987年、School Report というタイトルのチャリティ本が発売された。この本は、テレビ司会者やサッカー選手や政治家といった、イギリルの有名人の子供時代の通知簿や写真を掲載したもので、本の売り上げは小児病棟のボランティア組織に寄付される。この本に登場する約50名の有名人の中には、ダグラス・アダムスの名前もあった。
アダムスのコーナーは、見開き2ページ分。左側のページには、ブレントウッド・スクールの校庭とおぼしき場所に一人で立っているアダムスの写真が載っている。半ズボンの制服姿だが、この写真を見た限りでは、半ズボン姿にもそんなに不自然さを感じない。多分、周りに他の人がいないせいで、アダムスの身長の高さがピンとこないからだろう。
右側のページには、1964年の Michaelmas Term(1学期。ただし日本と違って9月始まりなので、9月から12月までの期間を意味する)、12歳当時のアダムスの成績表が転載されている。各教科の成績とその担当教員からの所感に加え、寮の先生や校長からのコメントなども書かれているが、いかんせん手書きの筆記体なのでものすごく読みにくい。結局、はっきりと分かるのは各教科の成績くらいで、「英語:B、数学:C、ラテン語:B、フランス語:C、歴史:C、地理:B、物理:C、化学:A、音楽:A、美術:A 健康状態:良好」。採点基準は不明だが、あまり優秀な成績とは思えない。
子供の頃の学校の成績について、アダムスは、1998年3月5日にBBCラジオ4で放送された、ラジオ・ドラマ版『銀河ヒッチハイク・ガイド』20周年記念の特別番組 Douglas Adams's Guide to the Hitchhiker's Guide to the Galaxy のインタビューの中で語っている。アダムスいわく、科目によって、すごく良くできるか全然できないかの両極端で、後になって考えてみると、その違いは内容についてきちんと理解できたかどうかによる、とのこと。多くの人は、意味もよく分からないまま丸暗記してやり過ごすことができるが、自分はそれができない。ひとたび意味が分かりさえすれば、ちゃんと憶えられるが、そうでない限りは頭に入らないのだ、と。
ブレントウッド・スクールの教師たちにも、アダムスができる時は飛び抜けて優秀なのにできない時はまったくダメになる理由がよく分からなかったようだ。「彼らは、僕がすごく頭がいいのか、あるいはどうしようもないバカなのか、決めかねていた」(Gaiman, p. 4)。
イギリスの教育制度では、義務教育修了時(日本の中学校卒業にあたる)に、15、6歳の子供たちは「Oレベル」(現在はGCSEという名称に変更)という全国統一試験を受けることになっている。大学進学を希望する生徒は8〜10科目を受けるのが一般的で、アダムスは10科目を受け、ギリシア語を除く9科目に合格した。アダムス本人が語っている通り、フランス語といいギリシア語といい、とにかく丸暗記しないことには始まらない外国語はかなり苦手だったということか。
Oレベルの試験に合格すると、今度はシックス・フォーム(Sixth Form)と呼ばれる大学進学に向けた2年間の教育課程(日本の高校2・3年に該当)に進むことになる。この課程では、大学入試のための全国統一試験、いわゆる「Aレベル」(正式名称はGCE-Aレベル)に向けた勉強をするが、「Oレベル」と違い、「Aレベル」の試験は大学での専攻に合わせた3、4科目を選んで受ける。ということはつまり、日本の高校生が文系志望/理系志望にかかわらず、外国語も数学も社会も理科もある程度まんべんなく勉強しなければならないのに対し、イギリスの生徒たちは、「Oレベル」の試験が終わった15、6歳の時点で、自分の将来の専攻を決め、そのための勉強だけをすることになる。
1968年、シックス・フォームに進学したアダムスが「Aレベル」の試験科目に選んだのは、中世史と近代史と英文学だった。ケンブリッジ大学に進学して、フットライツに参加して、ジョン・クリーズのようなライター兼パフォーマーになることを夢見る高校生としては、妥当な選択だったかもしれない。が、ライター兼パフォーマーになりたい、という希望とは別に、アダムスは、この時の自分の科目選択が正しかったかのどうか、後になって考えることもあったようだ。高校生のアダムスの中には、父方の祖先の系譜に従って医学を志すべきではないのかという気持ちも少しはあったらしい。1987年のインタビューでは、15、6歳の子供に文系か理系かのどちらか一方だけを選ばせるイギリスの教育システム自体、そもそも間違っているのではないかと語っている(Hitchhiker, p. 25)。
公式伝記によると、アダムスの「Aレベル」の試験結果は必ずしもよくなかった。この頃、初めてのガールフレンドができて、そのせいで勉強が二の次になっていたという。それでも、どうにか念願かなってケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジの奨学金を手にすることができた。非公式伝記には、アダムスがセント・ジョンズ・カレッジを選んだのは、父クリストファーの出身カレッジだったからだと書かれているが(同、p. 27)、公式伝記では断言を避けている節がある。
アダムスがケンブリッジ大学に合格したのは、「Aレベル」の成績もさりながら、大学に提出した宗教詩に関するエッセイが評価されたたためだった。アダムスに言わせれば、必死になって真剣に書いたというより、むしろやっつけ仕事に近い代物だった、とのこと。しかし、こだわる時にはこだわりすぎて一字も先に進めなくなるアダムスのことだから、普通の基準で考えればこのエッセイも決して「やっつけ仕事」ではなかったにちがいない。
エッセイの内容は、クリストファー・スマートとジェラルド・マンリー・ホプキンスとジョン・レノンの3人を関連づけた宗教詩の復活に関するものだった。クリストファー・スマートは、アダムスのケンブリッジ大学での主要研究テーマとなるが、後に「過激な無神論者」を自称するアダムスが、学生時代は宗教詩を研究していたのだからおもしろい。ブレントウッド・スクール時代のアダムスは、「過激な無神論者」どころか、むしろ信仰心の厚い生徒のうちの一人だった。父親のクリストファー・アダムスが大学で神学を学んでいたくらいだから、アダムスが育った環境はどちらかというと宗教色が強かったし、アダムス自身、American Atheist のインタビューに答えて、「敬虔なキリスト教徒だった」と認めている(The Salmon of Doubt, p. 97)。寮の同級生だったデイヴィッド・ウェイクリングも、ブレントウッド・スクールの寮生は毎週必ず日曜日の礼拝に行く決まりになっていたが、アダムスはどちらかと言うと率先して行くタイプだったと話している(Hitchhiker, p. 22)。
声変わりをするまでは、聖歌隊の一員として歌声を響かせていた。クリストファー・スマートの宗教詩『子羊欣唱』(Jubilate Agno)をケンブリッジ大学に提出するエッセイのテーマに選んだのも、この長大な詩の一部分を聖歌隊のコーラスでよく歌っていたという意味で、アダムスには馴染みのあるものだったから、という理由もあったらしい。先に書いた通り、ビートルズの「ブラックバード」を歌って顰蹙を買ったこともあったが、声変わりをした後も、教会の仕事を積極的に手伝っていた。1966年には、「Service in Chapel」という賞を受賞している。
1967年の Michaelmas Term になると、アダムスは学校の礼拝堂の聖具係に正式に任命された。(不心得な異教徒から見ると)単なる雑用係のような気もするが、M・J・シンプソンは非公式伝記の中で「ダグラスにとって、この学期中に起こったもっとも重要な出来事」(p. 24)と表現している。
当時、聖具係担当だった牧師は、トム・ガーディナー。ガーディナーいわく、聖具係としてアダムスはよく頑張っていたという。にもかかわらず、アダムスの聖具係としての日々は長くは続かなかった。寮の施設が充実していなかったこともあって、ガーディナーは、聖具係をしている生徒に勉強用として自分のオフィスを使うことを許可していたが、アダムスは勉強する代わりにオフィスに他の生徒を呼び込んでインタビューしたりしていたことが発覚する。この一件で、ガーディナーはアダムスを聖具係から外すことに決めた。
当然、ガーディナーとアダムスの関係は険悪化したが、だからと言ってアダムスはブレントウッド・スクールの教会に背を向けたりはしなかった。聖具係の仕事は失ったけれど、今度は聖歌隊の秘書として、聖歌隊長のジョン・ムーア=ブリジャーについて仕事をするようになる。
2002年、ムーア=ブリジャーはM・J・シンプソンのインタビューに答えて、当時のアダムスについて「彼ならソロを任せても大丈夫と思えるような、信頼できるタイプの生徒だった」(同、p. 25)と語っている。何だかトム・ガーディナーの記憶にあるアダムスとはまるで別人のようだが、多分、二人とも間違っていないのだろう——熱心に務めを果たそうとする(ムーア=ブリジャーの見解)が、時として熱心が高じて暴走してしまう(ガーディナーの見解)、と考えれば。
1970年12月、アダムスはブレントウッド・スクールを卒業した。ケンブリッジ大学に入学するのは1971年10月だから、約10ヶ月の「休暇」がある。いわゆる「ギャップ・イヤー」だ。
この10ヶ月を利用して、アダムスはイスタンブールへのヒッチハイクの旅を決行した。
たとえ安上がりなヒッチハイクの旅であろうと、それなりに旅の資金は必要である。という訳で、アダムスはアルバイトを始めた。まずはニワトリ小屋の掃除、それからサマセット州にあるヨービル総合病院(Yeovil General Hospital)でのレントゲン運び(レントゲン室で管理されているレントゲン写真を診療室等に持っていく係のことだろう。現在の大型病院ではレントゲン写真はデジタル化されているため、いちいち運ぶ必要はなくなったが)。
準備が整い、イスタンブールを目指してヒッチハイクの旅に出発したアダムスは、この旅の途中のインスブルックで初めて『銀河ヒッチハイク・ガイド』のアイディアを思い付いた。という話は、アダムス自身、インタビュー等でも繰り返し語っているし、アダムスが書いた『銀河ヒッチハイク・ガイド』の序文 "A Guide to the Guide: Some unhelpful remarks from the author." の中でも明記されている。しかし、このエピソードはあまりに出来すぎていて、本当に事実なのかと疑問視する向きもあるらしい。アダムス自身、何度も同じエピソードを語りすぎたせいで、実際に起こったことなのか、はたまた自分でそう思い込んでいるだけなのか、いつしか心許なく感じることもあったようだ。私は『ヨーロッパ・ヒッチハイク・ガイド』だけを手に、原っぱに行って寝転がったのだが、空に星が出ているのを見て、ふと思った。誰かが『銀河ヒッチハイク・ガイド』という本を書いてくれたら、少なくとも自分は一散で飛んでいくのになあ。こう考えて、私はすぐに眠りに落ち、このことは6年間忘れていた。
誰かが、アダムスのギャップイヤーの旅を徹底的に調査したとする。アダムスがイスタンブールに向けてヒッチハイクの旅をしたことは事実でも、本当に旅の途中でインスブルックに寄ったのか、たとえインスブルックに寄ったとしても、当時、インスブルックの市街地からそう遠くない場所に、酔っぱらって寝転がっていられるような原っぱは実在したのか。そもそも本当にアダムスはこの旅に『ヨーロッパ・ヒッチハイク・ガイド』という本を持参していたのか。
厳密な調査の結果、事実はアダムスの証言と食い違っていた、という可能性はある。ヒッチハイクの件に限らず、アダムスはこの手の「よく出来たエピソード」のレパートリーをいくつか持っていた。アダムスにとっては、読者や聴衆を惹き付けるおもしろい話に仕上がっているかどうかが肝心なのであって、そのために事実関係の細部に少々手を加えることがあったかもしれない。そして、同じエピソードを何度も何度も繰り返して話すうち、細かいディテールのうちのどこまでが事実でどこからが創作なのか、自分でもよく分からなくなった、ということもありえただろう。でも、だからと言って「嘘つき」呼ばわりされるのは、アダムスにとっては心外ではないだろうか。これまでに出版された3冊のダグラス・アダムス伝のうち、ニール・ゲイマンの Don't Panic: Douglas Adams & The Hitchhiker's Guide to the Galaxy だけは、アダムスの生前に出版された。故に、アダムス本人と直接対話し、アダムス本人が提供した資料を使い、アダムス本人も読むことを前提として書かれている。そのため、推測や伝聞の類は一切なし、裏付けの取れる事実関係を別にすれば、アダムスの言葉はあくまで「アダムスの言葉」として扱われ、それが事実か否かを問うことはしていない。
それに対し、アダムスの死後、2003年に出版されたM・J・シンプソンの Hitchhiker: A Biography of Douglas Adams は、アダムスや『銀河ヒッチハイク・ガイド』にまつわる「よく出来たエピソード」を徹底検証している。その結果、ヒッチハイクの旅のエピソードを含め、これまでは事実だと思われていたものが、実際はそうではなかったらしいということが明らかになった。
非公式伝記の発売から約7ヶ月後、公式伝記 Wish you were here: the Official Biography of Douglas Adams が出版された。この本の中で、ニック・ウェブは、M・J・シンプソンが非公式伝記で採用したようなアプローチに対し、ささやかな抗弁を試みている。ニール・ゲイマン、M・J・シンプソン、ニック・ウェブによる、三者三様のダグラス・アダムズ伝は、同じ人物を異なる立場と視点で描いている。だから、誰の伝記がアダムスの実像にもっとも肉薄しているかを決めることはできない。それぞれの認識のギャップを丹念に拾い上げることが、今の私にできる精一杯であり、現状の成果がこの文章である。Douglas had a repertoire of anecdotes that he used to great effect on the promo circuit and at c the conventions and conferences. He always told these stories in exactly the same way, right down to the comic hesitations as he appeared to rummage around his cortex for exactly the right word. Before you scoff, this is not something to elicit cynicism, but admiration. Douglas was a frustrated performer with a perfectionist streak. The appearance of effortless wit is not effortless at all. He liked to entertain, and if he had polished a yarn to the point where it could not be improved he felt he owed it to his listners to treat them to the best version. The danger of this approach is that a kind of unreality about the original experience creeps up on the teller.